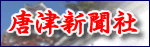![]()

お祭り・イベント
情報提供/唐津市役所・唐津観光協会
唐津くんちの曳山について
城下町としての唐津の町は、慶長の頃(西暦1600年頃)寺沢志摩守広高が唐津城を築いた時に始まりますが、唐津っ子の産土神(うぶすながみ)である唐津神社の秋祭は、築城前の古くから行われていました。町人衆の篤い敬神の誠は、文政2年(1819年)刀町の赤獅子の奉納に現われ、以来明治9年までの57年間に15台の曳山が次々とん奉納され(うち紺屋町の黒獅子は明治中期に損滅)これらの貴重な町人文化の遺産は、幾多の苦難に耐えて守り継がれ、曳き続けられてきました。
豊穣の秋祭「唐津くんち」は、毎年11月3・4日に行われていますが、2日の夜は宵曳山(よいやま)と呼び、14台の曳山は飾り提灯に彩られ、万燈に映える金銀丹青(たんせい)も鮮やかに華麗なる巡行が展開されます。
翌3日(文化の日)は、唐津大明神が御旅所(おたびしょ)へ御神幸される日で、御輿(みこし)に供奉(くぶ)する曳山は、江戸時代の町火消装束を今に伝えて、黒木錦の腕貫・腹掛・股引等に身を固め、各町ごとに意匠をこらした。
いなせな法被(はっぴ)姿の曳子たちが、鐘・笛・太鼓の勇壮豪快な曳山囃子につれてある時は走り、ある所は緩く市中の巡路を引き廻ります。
なかでも御旅所のある西の浜での曳込みは「唐津くんち」の圧巻で、重さ2〜4トンもある曳山が轍(わだち)も深く競い合い、死力を尽くして砂地に挑むその姿は、壮快無比な景観であり、数万の観衆を魅了します。
続く4日は御神幸はなく町民の祭りとして、ほぼ前日と同じ町々の巡路をゆっくりと引き廻りますが、「乾燥造」と呼ばれる工法によるこの曳山は、木組み・粘土の原型や木型の上に和紙を数百回張り重ね、麻布を張り、幾種類もの漆で塗り上げ、金銀を施して仕上げたもので、完成までには2年前後の歳月を要したと伝えられています。多種多様な姿態の造形美は稀に見る優れた工芸品として、佐賀県の重要有形民族文化財に指定されています。
お祭りのとき以外は、曳山展示場にて曳山を見学できます
唐津くんち・曳山の紹介
 一番曳山 刀町の赤獅子 (製作 1819年・文政2年) |
 二番曳山 中町の青獅子 (製作 1824年・文政7年) |
 三番曳山 材木町の亀と浦島太郎 (製作 1841年・天保12年) |
 四番曳山 呉服町の九郎判官源義経の兜 (製作 1844年・天保15年) |
 五番曳山 魚屋町の鯛 (製作 1845年・弘化2年) |
 六番曳山 大石町の鳳凰丸 (製作 1846年・弘化3年) |
 七番曳山 新町の飛龍 (製作 1846年・弘化3年) |
 八番曳山 本町の金獅子 (製作 1847年・弘化4年) |
 九番曳山 木綿町(きわたまち)の 武田信玄の兜 (製作 1864年・元治元年) |
 十番曳山 平野町の上杉謙信の兜 (製作 1869年・明治2年) |
 十一番曳山 米屋町の酒呑童子と源頼光の兜 (製作 1869年・明治2年) |
 十二番曳山 京町の珠取獅子 (製作 1875年・明治8年) |
 十三番曳山 水主町(かこまち)の鯱 (製作 1876年・明治9年) |
 十四番曳山 江川町の七宝丸 (製作 1876年・明治9年) |
観光・宿泊 ・ グルメ情報(食べる・飲む) ・ ショッピング ・ 美容・医療・介護
暮らし・生活と文化 ・ 各種サービス ・ 趣味・サークル・スクール ・ 公共施設
企業・団体 ・ マニア・その他 ・ びびっと!からつ ホーム